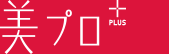美容スペシャリストな自分になるために
作成:2025.02.20
結婚式で活躍する着付け師の仕事内容と1日の流れ

結婚式での着付け師は、新郎新婦や列席者の和装を美しく整える重要な役割を担っています。特に和装の婚礼衣装は複雑で専門的な技術が求められるため、着付け師の存在が欠かせません。結婚式で活躍する着付け師の仕事内容や1日の流れ、さらに着付け師になるためのステップについて詳しくご紹介します。思いきって、ブライダル業界に飛び込んでみてはいかがでしょうか。
INDEX
■着付け師の主な仕事内容
■ヘアメイクスタッフとの連携
■着付け師の1日の流れ
■着付け師に求められるスキルと魅力
■着付け師になるには?
■まとめ
着付け師の主な仕事内容

結婚式における着付け師の役割は多岐にわたります。和装の美しさを最大限に引き出し、長時間着用しても苦しくないよう配慮しながら仕上げることが求められます。また、新郎新婦だけでなく、結婚式に出席する人々へ着付けをすることもあります。そのため、対象となる人の年齢層も幅広く、それぞれ注意しないといけないことがあるかもしれませんね。
新郎新婦の着付け
結婚式において最も重要な着付けの対象は新郎新婦です。特に新婦は、白無垢や色打掛、引き振袖といった華やかで重厚な衣装を着るため、時間をかけて慎重に着付けを行う必要があります。新郎新婦にとって大切な1日になるため、着崩れするようなことがないようにしなければなりません。
白無垢の着付け
神前式で用いられる白無垢は、格式高い装いのため細かく注意を払って仕上げていきます。重ね襟のバランスや襟元の美しいラインを整え、裾の長さを計算しながら仕上げます。デザインがシンプルだからこそ、ごまかしが利かないのかもしれませんね。
色打掛の着付け
色鮮やかな刺繍や金糸があしらわれた色打掛は、格式を保ちつつ華やかさを際立たせる必要があります。着付けが終わり、華やかな色打掛を身にまとう花嫁の姿を見ると、実に美しく圧巻です。
新郎の紋付袴の着付け
新郎の紋付袴はシンプルながらも、シワをなくし、凛々しく見せる着付けスキルが必要です。裾の長さや羽織のバランスにも注意を払います。新婦だけが主役ではなく、和装は男性を引き立たせる力があるので、きちんと紋付袴を着こなせていることで印象が大きく変わります。
親族・列席者の着付け
親族や列席者も和装を選ぶことが多く、着付け師が活躍する場の一つとして挙げられます。主役の新郎新婦を担当するのはもちろんのこと、当日の朝、遠方から多くの列席者が訪れます。全員のお支度を受け持って、結婚式に間に合わせる必要があります。
留袖の着付け
既婚女性が着る留袖は、格式高い装いであり、裾模様の位置が整っていることが重要です。帯結びはふくら雀など格式のある形を選びます。
振袖の着付け
未婚女性が着る振袖は、袖の長さを活かした華やかな帯結びが特徴です。帯の形を変えて個性を出すこともあります。
訪問着の着付け
訪問着は幅広い場面で着用されるため、華美すぎず品のある着付けが求められます。肩から裾にかけて流れるように描かれた絵羽模様が特徴です。また、縮緬や綸子、紬など、様々な種類の生地を使った訪問着があるのも特徴です。
ヘアメイクスタッフとの連携

着付け師はヘアメイクスタッフと密接に連携し、新婦のトータルコーディネートを完成させます。例えば、ヘアセットの高さに応じて襟元の見せ方を調整するなど、細かな調整が求められます。着付け師が一人で仕上げるものではないので、ある意味やりがいを感じられるかもしれませんね。
着崩れ防止と補正
和装は時間が経つと着崩れしやすいため、長時間美しい状態を保てるよう工夫が必要です。着崩れ防止のために補正を行い、体型に合わせたフィット感を持たせることで、着心地を良くしながらも美しいシルエットを作ります。
衣装のチェックと最終確認
小物の準備や帯結びの最終チェックを行い、細部まで整えます。例えば、半襟の位置や帯締めの結び方、草履のフィット感などを丁寧に確認します。
リハーサルでの試着
事前に着付けの練習を行い、当日のスムーズな進行を確保します。新郎新婦に実際に和装を着てもらい、着付けの時間を計測しながら微調整を行います。
着付け師は単なる技術者ではなく、お客様が安心して式に臨めるよう心のケアも大切な仕事の一部です。
着付け師の1日の流れ
結婚式当日は、朝早くから準備が始まります。着付け師の1日は以下のような流れになります。
1. 早朝:会場入りと準備
- 会場に到着し、道具や衣装の確認を行う。
- 事前にスケジュールを確認し、ヘアメイクスタッフと打ち合わせを行う。
- 必要な補正アイテムや帯枕などの準備を整える。
2. 新婦・新郎の着付け
- まずは新婦の着付けを行う。白無垢や色打掛の着付けには時間がかかるため慎重に進める。
- 新郎の紋付袴の着付けを行う。
- 仕上げの際に、ヘアメイクスタッフと微調整を行う。
3. 親族・列席者の着付け
- 招待客の着付けを順次行う。
- 留袖や振袖は、着崩れしにくいように帯の結び方を工夫する。
4. 挙式・披露宴中のサポート
- 挙式前に最終チェックを行い、着崩れがないか確認する。
- 必要に応じて、衣装の直しや補正を行う。
- 披露宴でのお色直しがある場合は、迅速に対応する。
5. 片付けと撤収
- 使用した衣装や小物を整理し、会場を片付ける。
- 必要があれば新郎新婦や列席者の着替えをサポートする。
- 1日の流れを振り返り、次回に向けた準備を行う。
着付け師に求められるスキルと魅力
着付け師として活躍するには、専門的な技術と経験が必要ですが、それ以上に大切なのは「美しく着せるだけでなく、心地よく着せる」ことです。
正確で迅速な着付け技術
着物の着付けは、細かな手順が求められるため、正確さが重要です。また、結婚式当日は時間との勝負でもあるため、素早く的確に着付けるスキルが必要になります。帯の締め方一つで着心地や見た目が大きく変わるため、豊富な経験と練習が不可欠です。
和装に関する深い知識
和装には様々な種類があり、それぞれに適した着付け方法が存在します。例えば、振袖と訪問着では帯の結び方が異なりますし、季節によって適切な素材や小物選びも異なります。着付け師は、こうした和装文化に関する深い知識を持ち、お客様に最適な着こなしを提案することが求められます。
細やかな気配りと接客スキル
結婚式当日は、新郎新婦だけでなく親族やゲストの緊張も高まるため、着付け師はただ技術を提供するだけでなく、安心感を与える存在であることが求められます。着物を着る際の不安や疑問に寄り添い、心地よく過ごせるような接客スキルが大切です。
体力と集中力
着付けの仕事は意外にも体力が必要です。特に結婚式では、長時間立ちっぱなしで作業が続くため、持久力と集中力が求められます。さらに、ミリ単位の細かい調整が必要なため、一瞬たりとも気を抜くことができません。
結婚式は人生の大切な節目。その場に立ち会い、晴れの日を支える着付け師の仕事は、やりがいと喜びに満ちたものです。
着付け師になるには?
着付け師になるためには、専門的な知識と技術を身につける必要があります。以下のステップを踏むことで、プロの着付け師として活躍できるようになります。
1. 着付けの基礎を学ぶ
着付け教室や専門学校で基本的な技術を学ぶことが大切です。初心者向けのコースからプロ養成講座まで、さまざまなプログラムが用意されています。
関連記事:美容専門学校を選ぶことから始めましょう
2. 資格を取得する
必須ではありませんが、着付けの資格を取得すると信頼性が増します。代表的な資格には以下のようなものがあります。着付け師になるにあたり、資格取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。
- 着付け技能検定(国家資格)
- 着物免許(民間資格)
- きもの講師(民間資格)
- 着付け師(民間資格)
- 着付講師認定証(民間資格)
- 着物着付講師(民間資格)
- きものスペシャリスト技能検定(民間資格)
- きものコンサルタント(民間資格)
関連記事:着付けに関する資格を徹底解剖!
3. 現場経験を積む
実際の現場で経験を積むことが重要です。美容室や結婚式場、着付け専門のサロンでアシスタントとして働くことで、実践的な技術を磨けます。いきなり即戦力として働くことを考えるとどうしてもハードルが高く感じますが、現場経験を積んでいくことで自信に変わっていきますよ。
4. 独立・フリーランスとして活動する
経験を積んだ後は、独立してフリーランスの着付け師として活躍することも可能です。SNSやウェブサイトを活用して集客し、自分の顧客を増やすことが成功の鍵となります。着付け師が活躍する場として、成人式や結婚式が考えられますが、どちらも一度きりになる人が多いので、集客というよりも結婚式場や着付けサロンとのパイプを増やしておくと良いのかもしれませんね。
まとめ

結婚式での着付け師は、和装の美しさを引き出すプロフェッショナルとして重要な役割を果たします。朝早くからの準備や着崩れ防止、衣装チェンジなど、多忙ながらも達成感のある仕事です。技術だけでなく、人との関わりを大切にすることで、新郎新婦や列席者の特別な1日をさらに輝かせることができるでしょう。
また、着付け師になるためには、基礎を学び、資格を取得し、現場での経験を積むことが不可欠です。確かな技術と接客スキルを身につければ、着付け師として活躍できる道が広がります。
この記事に関連するキーワード
関連求人を探す